音楽の常識を“理系の目線”で読み解いてみた
「ドレミファソラシド」は、音楽を習った人なら誰でも知ってる言葉です。
でも考えてみてください。なぜ“7つ”の音なのか? “8つ”じゃダメなのか?
“無限”に音の高さはあるのに、なんで決まった数だけなのか?
楽器を練習する中で疑問に思い、調べてみました。
本記事では、音階の起源やその根底にある理論、長調と短調の意味について調べてみました。
ドレミの起源はピタゴラスにあった!
音楽の音階のルーツは、紀元前のギリシャ時代にさかのぼります。
「三平方の定理」で知られるピタゴラスが、弦の振動を観察して音の高さの関係を発見しました。
- 弦の長さを半分にすると、オクターブ上の同じ音になる(たとえばド → 高いド)
- 弦の長さを3分の2にすると、「ソ」の音になる(ドと協和する)
このようにして彼は「協和音」とされる音を数学的に割り出していきました。
そしてここで登場するのが「完全5度(かんぜんごど)」という考え方です。
🔍 補足:完全5度って何?
「完全5度」とは、ある音から数えて5番目の音(ド → ソなど)のことで、
その2つの音が鳴ったときに、とても“安定して心地よい響き”になる組み合わせです。
この「ドとソ」「レとラ」など、2:3の周波数比を持つ音の関係が「完全5度」と呼ばれます。
ピタゴラスは、この「完全5度」の関係を使って、音をどんどん積み上げていきました。 たとえば…
- ドから完全5度上は ソ
- ソから完全5度上は レ
- レからまた完全5度上は ラ
…というふうに繰り返していくと、最終的に12個の異なる音が出てきて、 これが今私たちが使っている「1オクターブ12音」のもとになったのです。
ちなみに「1オクターブ12音」とは、ドから始まり高いドまでの間に、半音を含めて12の音があるという仕組みです。
(ここでいう「半音」とは、音と音のあいだの最も小さな距離(音程)を指します。ピアノの鍵盤で言えば、隣り合う白鍵と黒鍵の間や、ミとファ、シとドのように黒鍵を挟まない隣接音も含めて「1鍵分」が半音になります。)
ピアノの鍵盤でいうと、白鍵と黒鍵を合わせて12個のキーが1オクターブに存在しています。
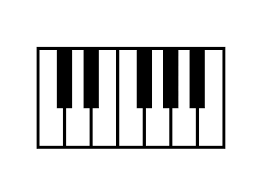
でも問題が発生…「一周したら戻らない!?」
ピタゴラスの音律、理論的には完璧に見えますが、
完全5度を12回繰り返すと「7オクターブ上のド」に戻るはずが、実際にはわずかにずれが発生することが知られています。
補足:なぜ一周したのにズレるの?
「完全5度を12回積み上げれば、最初のドに戻るはず」と思いきや、実際には微妙に音が高くなってしまいます。これは、音の周波数比が「2:1(オクターブ)」と「3:2(完全5度)」という異なる比率に基づいているためです。
「2:1」は、ある音の周波数を倍にしたときに得られる音で、オクターブ上の同じ音を意味します(例:ド→高いド)。
一方「3:2」は、協和音として知られる完全5度の周波数比で、たとえばドとソの関係がこれに当たります。
この2つの比率は数学的に独立した値であり、片方を何度重ねてももう片方に完全には一致しません。具体的には、3:2 の完全5度を12回重ねた結果(つまり (3/2) の12乗)と、2:1 のオクターブを7回重ねた結果(つまり 2⁷)は、理論的には一致しないのです。その微妙なずれが「ピタゴラスコンマ」と呼ばれる現象につながります。
この比率を使って12回5度を積み重ねると、「1オクターブ×7」よりも少し高くなってしまい、元の音にぴったり戻れないのです。このズレは「ピタゴラスコンマ」と呼ばれ、音楽理論上の重要な課題のひとつでした。
数学的には協和する音を積み重ねると、どこかで“破綻”するという結論に至ります。
ピタゴラスはこの問題を“近似”でごまかしましたが、 それでも「転調ができない」「ドとミが美しく響かない」といった限界が残ってしまいました。
響きの美しさ vs 音楽の自由
ここから、響きを取るか、転調の自由を取るかで音楽理論が分かれていきます。
- 純正律:美しい響きが得られるが、転調に弱い
- 平均律:どんな調にも転調できるが、音の美しさは若干犠牲に
たとえば平均律では、全ての半音の幅を均等にし、どの調でも同じ構造のスケールになるように設計されています。
この進化の過程が、バッハの《平均律クラヴィーア曲集》などに象徴される内容になります。
音階の起源は
実際、人の耳や声は連続的な音の変化を認識できます。 でも「ド」「レ」「ミ」などの限られた音だけを選び、そこにルールをつけた。
音階とは、ピタゴラスの理論に基づきつけられたルールにほかなりません。
そもそも「ドレミファソラシド」という名前の起源は、中世ヨーロッパにまでさかのぼります。
11世紀、イタリアの修道士であり音楽教育者でもあったグイード・ダレッツォは、聖ヨハネ賛歌「Ut queant laxis」の歌詞に着目しました。この賛歌の各節は、それぞれ1音ずつ音階が上がっていく構成になっており、グイードはその最初の音節を使って階名として定着させようと考えました。
その結果、生まれたのが「Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La」という6音の階名です。これが当時の「ヘクサコード(6音音階)」の基本となりました。
しかし「Ut」は発音しにくかったため、のちにラテン語で“主(しゅ)”を意味する「Dominus(ドミヌス)」の頭文字を取って、「Do(ド)」に置き換えられます。
さらに、賛歌の最後に登場するフレーズ「Sancte Iohannes(聖ヨハネ)」の頭文字「S」と「I」を組み合わせて「Si(シ)」が追加され、ようやく現在の7音階「Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si(→日本語でドレミファソラシ)」が完成したのです。
このようにして生まれた「音の名前」が、世界中で使われる音楽の共通語になっていきました。
その背景には、西洋音楽の記譜法や音楽理論が世界的に普及したことがあります。中世から近代にかけて、西洋クラシック音楽が教育や宗教、演奏文化を通じてヨーロッパ全土に広がり、さらに植民地支配や国際的な交流によって世界中に伝わっていきました。特にグレゴリオ聖歌をはじめとする教会音楽では、階名を使った視唱が広く取り入れられたため、「ドレミ」は音楽教育の標準語のような存在となったのです。
さらに、20世紀に入ってからもソルフェージュ(音感教育)においてこの体系が広く使われ続け、国や言語を越えて音楽を学ぶ上での“共通言語”として定着していきました。
長調・短調はどういう意味か
音楽を習っていると長調や短調が出てきて、しかもものすごい種類があり、
どういう意味なのか疑問になります。
長調・短調にはそれぞれ12種類ずつ存在します。
ここでいう「長調」とは、明るくはっきりとした響きを持つ音階で、「ドレミファソラシド」のような順序が基本です。一方「短調」は、やや哀愁を帯びた響きを特徴としており、「ラシドレミファソラ」のような音の並びが基本になります。
音楽理論では、すべての半音ごとに1つの調性が存在し、それぞれが長調と短調を持ちます。
長調の例(C, G, D, A, E, B, F♯, C♯, F, B♭, E♭, A♭)
短調の例(A, E, B, F♯, C♯, G♯, D♯, A♯, D, G, C, F)
このように12音からなる音階ごとに長調・短調があるため、全部で24の基本的な調があります
(さらに、変化調や転調を含めるともっと多様な組み合わせが生まれます)。
例えばイ長調(Aメジャー)は、シャープが3つ(F♯, C♯, G♯)付く明るい響きの調で、ピアノや弦楽器でも演奏しやすく、
クラシックからポップスまで幅広く使われています。
イ長調の音階構成は、イ・ロ・ハ・ニ・ホ・へ・ト(日本語音名)で、英語表記では A – B – C♯ – D – E – F♯ – G♯ – A となります。
これらの音は全音と半音の規則(全-全-半-全-全-全-半)に従って並んでおり、明るくはっきりした印象を作り出します。
(1オクターブ12音をドレミファソラシドの7音で表現するため、半音と全音(半音2つ分)が混ざった並びになる)
イ長調では
- 自然短音階(ナチュラルマイナー)
- 和声短音階(ハーモニックマイナー)
- 旋律短音階(メロディックマイナー)
という3種類があります。
自然短音階は、長調の平行調としてシンプルに構成されており、音の間隔も素直です。
「平行調」とは、同じ音階の構成音を共有しながら、主音(音階の出発点)が異なる長調と短調のペアのことを指します。たとえば、ハ長調(Cメジャー)とイ短調(Aマイナー)は、どちらも同じ7つの音(C, D, E, F, G, A, B)を使用しますが、出発点が異なるため響きや雰囲気が異なります。
平行調は、転調や音楽の展開の際によく使われる関係性で、音楽理論の基本のひとつとなっています。
ここでいう「音の間隔が素直」とは、音と音のあいだの距離(音程)が極端に広すぎたり狭すぎたりせず、全体として滑らかで無理のないステップで構成されているということです。たとえば、音階が全音-半音-全音…といったように、聞いたときに自然な流れとして感じやすく、旋律として無理のないラインを描ける構造になっています。
ただし、主音に対して導音(解決へと引っ張る音)が不足しており、旋律的に少し弱さを感じる場面があります。ここでいう「導音」とは、音階の7番目の音にあたり、主音に向かう強い引力(解決感)を持つ音のことです。自然短音階ではこの導音が半音下ではなく全音下にあるため、主音への引力が弱く、音楽的に終止感や緊張感を持たせにくいことがあるのです。
その問題を解決するために、7番目の音(例:イ短調ならソ)を半音上げてシャープさせたのが和声短音階です。
これにより、ラ(主音)に向かうソ♯が導音の役割を果たし、強い解決感が得られるようになります。
ただし、和声短音階では「ファ→ソ♯」の間隔が広く、不自然な跳躍が生まれてしまいます。
これを滑らかにするために考案されたのが旋律短音階で、上行時には6番目と7番目の音をどちらも半音上げて滑らかなラインを作り、下行時には自然短音階に戻すという非対称な使い方がされます。
このように、短調の3形は「音楽的な流れの自然さ」を保ちつつ「機能的な役割」を果たすために、時代を超えて工夫と試行錯誤が繰り返されてきた結果なのです。
まとめ:ドレミは“自然”でも“必然”でもない
「ドレミファソラシド」という音階は、長い歴史と数えきれない工夫の上に成り立っている人工物にほかなりません。
美しさ、便利さ、そして人間の感覚や文化に合わせて進化してきたもので、楽器の学習に必要不可欠なものですが、
あくまでも理論にほかならないことを理解しておく必要があります。
チェロでは、指番号=半音となるので、特に意識しておいた方が学習の役に立つのではないでしょうか。
今後の練習の参考になれば幸いです。
▼参考にした書籍
- 『音階はなぜ7つなのか』
(著:核融合研究者 × ジャズ愛好家) (ブルーバックス/理系的に音楽を読み解く異色本)


コメント